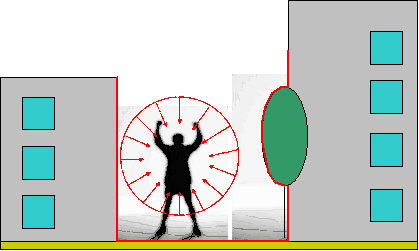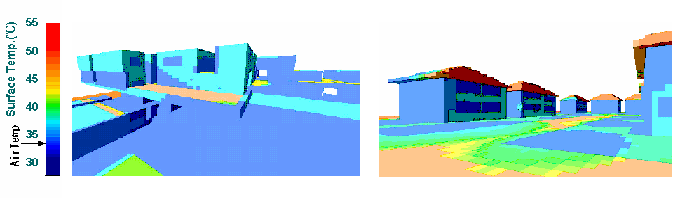サーモグラフィの応用編,第3弾です.
ここでは,私たちの都市について考えてみましょう.
「再放射」という言葉,少し理解できましたか?
「太陽光があたって,物の表面温度が上がって,そこから赤外線が放射される」ことですね.
これが人に当たると,人は「暑い」と感じることになるのです.
あなたが,建物に囲まれたところに立ったときのことを考えてください.上の図のように,周りの表面温度が高いと,再放射された赤外線をたっぷり受け取ります.
夏の昼間ですと,ただでさえ気温が高いのに・・・熱射病にはなりたくないですね!
そうそう,ちょっと「赤外線の目」で街を歩いてみましょうか・・・
(これをクリック! ↑)
動画について考えてみましょう.
これは,サーモグラフィを持って街を歩いたときのようすをコンピュータで作り出したもので,場所は架空の都市です...さて,これをみると,どんなことがわかりますか?
ちなみに,道路の表面温度がときどき低くなっているのは,上に樹木があって,木陰になっているところです.
道路の温度,55℃以上ですね.でも,木陰に入ると少し気温に近づいて40℃ぐらいになっています.建物の壁は...まあ気温に近いですね.夏の昼間ですから,太陽が真上にあって壁の温度があまりあがらないんです (たぶん,夕方になるとまた状況が変わるはずですが...).
さて,上の図にある温度のスケールバーをよくみてください.AirTempとあるのは,このときの気温です.気温は,日向でも日陰でも,街の中ではそんなに変わらないんですね.だけど表面温度は,一番低くて気温に近く,一番高いところでは気温より20℃以上も高くなっています.
・・・そうなんです!街を歩く人にとって,気温は同じでも,まわりの表面温度が低いと,体感温度はかなり下がるのです!!!
まちじゅうの気温を下げるのは難しそうですが,表面温度なら,植栽とか水とかをつかうと,何とかなりそうだとは思いませんか?・・・「都市が暑い」といわれていますが,なにやらこのあたりに解決方法がありそうな気が・・・
[コラム] 体感温度はなにで決まるのか
この教材でたびたび「体感温度」の話がとびだしてきました.どうも「体感温度」なるものは,気温とは同じではないみたいだ...とおもったキミ,実はその通りなのです.
体感温度は,もちろん個人差まで考えると大変微妙な問題でもあるのですが,一般的には「環境4要素」あるいは「環境6要素」といわれているものを考えて「体感温度」をコンピュータで計算しながら,建物を設計することが多いのです.
■「環境4要素」とは・・・気温(℃),湿度(%),平均放射温度(℃),気流(m/秒)
例えば,同じ気温でも「からっとしている」ばあいと「じめっとしている」場合がありますよね.これは空気中の水分量が違うからで,それによって体感温度も変わってきます...平均放射温度とは,いままで見てきたとおり,人を取り囲む周りのものの表面温度の平均値のことで,「再放射」の話はここに関係していたのでした!...そして,気流は?まあわかりますよね.気温は同じでも,扇風機の前は涼しいですよね!
■「環境6要素」とは・・・上記4つ+着衣量(clo)+代謝量(met)
もう少し厳密に体感温度を計算しようとすると,何を着ているか(着衣量)とか,そもそも体温が高くて汗っかきか(代謝量),といったところまで数値化して,コンピュータに入力します...

さらに厳密に考えれば,子供と成人,そして老人では体格も違いますし,男女の差も大きい場合もあるそうです.
例えば,「小学校」と「老人ホーム」では,設計方法が全くかわってくるわけですね...う〜ん,奥が深そうです.
(・・・さあ,どうでしょうか.あなたも環境にやさしい建物を設計できる「建築家」になりませんか?(笑))